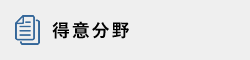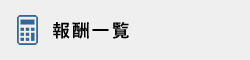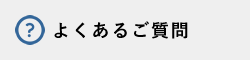- ホーム
- こうべみなと社労士オフィスの得意分野
- ハラスメント対応・対策サポート
ハラスメント対応・対策サポート
ハラスメント問題の実態把握から、未然に防止するルールづくりまで、御社の職場の信頼関係づくりをトータルにサポートします。
- 注意しても改善しない社員に担当替えを命じたら、パワハラだと訴えてきた…
- 前任の退職に伴い他部署から異動させた社員に同じ仕事量を渡したら、過大だと訴えてきた…
- 素行が悪く、陰口が多い社員が、上司から「やめてしまえ」と言われた。と訴えてきた…
- 上司は部下のためと思い、熱血指導をしてきたが「怖くて会社に行けない」と訴えてきた…
- 憧れの上司に飲み会で身体を触られ、悩み始め、そのままうつ病なってしまった社員…

日本でも最近、セクハラ 、パワハラ 、モラハラ、マタハラ等の「ハラスメント」の内容が社会的に認知されてきました。
法整備(パワハラ防止法は、大企業は、2020年6月、中小企業は、2022年4月から)も進み、何が「ハラスメント」に該当して、何が該当しないかがだんだんと明確になり、訴えられるケースが増えた一方で、企業の対処もしやすくなってきました。
しかし、私がハラスメント対応の相談窓口業務を行なっていて感じたのは、そもそも、ハラスメント(嫌がらせ)の関係になる前に、既に人間関係が壊れているケースが多いということです。
ハラスメントの基準を設定する前に、職場の人間関係=信頼関係づくりに取り組まなければ、ハラスメントの根源を断つことはできないと考えます。
こうべみなと社労士オフィスでは、ハラスメント問題の実態把握から、相談窓口の設置、ハラスメント問題を未然に防止するルールづくりと社員に対しての説明、ハラスメントに対する社員の意識を高める研修まで、御社の職場の信頼関係づくりをトータルにサポートしています。
こじれる前に、ご相談ください。
ハラスメントが起きにくい職場づくりをはじめましょう。
こうべみなと社労士オフィスが、ハラスメント対応と対策でお手伝いできること
ハラスメントに関する社内アンケートの実施

ハラスメントに関する社内アンケートを作成し実施します。
アンケート実施により、社内 のハラスメントに関する認識の差、知識の差、現状について把握することが可能です。
男女や年齢によりハラスメントに関する感覚の違いがみられます。
こうした違いを社内で共有することでハラスメントの防止につなげます。
審査基準を使用した社内のハラスメントの把握

職場におけるハラスメントについて必要な対策をとることは事業主の義務とされています。
必要な対策をとるためには、社内のハラスメント対策について把握することが必要です。
ハラスメント対策企業認証に基づいた審査基準の項目を確認することで、社内のハラスメント対策の現状を知ることができるとともに、「ハラスメント対策企業認証マーク」が取得できます。

ハラスメント対策企業マーク
ハラスメント対策企業マークとは、企業がハラスメント防止および発生時に適切な対応ができる体制づくりを行っていることを証明するためのマークです。
マークを付与された企業は、企業HPや各種広告物、名刺などにマークを使用して頂くことが可能です。
マークを掲載することにより、外部からの信頼、他社との差別化を図ることが可能です。
ハラスメント外部相談窓口

ハラスメント相談窓口とは、外部にハラスメント相談窓口を設置し、相談しやすい環境を整えることです。
専門のスタッフ(ハラスメント相談員養成講座修了)が対応にあたります。
外部にハラスメント相談窓口を設けることで、相談しやすい環境を整えるとともに、ハラスメント防止を図ります。

ハラスメント研修
例えば以下のような研修を、御社の状況とご要望に応じてカリキュラムを組み替えて行っています。
管理職向けパワーハラスメント研修
パワーハラスメントとは具体的に何なのか、どのような点に気をつけなければならないのかを、企業の要である管理職にお伝えする研修です。
- 職場のパワーハラスメントとは何かを知る
- パワーハラスメントが企業経営に与える影響について学ぶ
- 部下指導とパワーハラスメントの違いについて理解する
- 部下から相談を受けた場合の適切な対応を学ぶ
- パワーハラスメント防止のための管理職の役割を理解する
こうべみなと社労士オフィスのハラスメント対応・対策の特徴
| 特徴 01 | 人間関係を円滑にするという視点で、対応やルール作りに取り組みます 経営者・社員双方の「想い」を十分に聞き取り、双方が納得し同じ方向を向いて働くことができる「基準」としてのルールづくりをご提案しています。 |
|---|---|
| 特徴 02 | ハラスメント相談員の資格を持つ職員が対応します NPO法人ハラスメント協議会の「ハラスメント相談員養成講座」を修了した、ハラスメントについての専門知識を要する男性と女性が実際のハラスメント対応、相談、対策にあたります。 |
| 特徴 03 | 最新の同業他社や異業種の事例やとりくみをご紹介 これまでの経験を元に同業他社や異業種のハラスメント事例や取り組みをご紹介し、御社の戦略や風土にあった対応や対策づくりのヒントを提供します。 |
普通の業務の偏りやねぎらいがハラスメントに
精密加工機器のメンテナンスと部品供給を行うC社様。
どうしても毎月のある時期に事務処理が過大なる部署がありました。
この部署の上司は、過大な事務処理による残業をねぎらい、その日は女性社員を含む部下を食事に誘っていました。
しかし、この部署の女性職員が「仕事が過大に与えられた上、断ったのに食事にしつこく誘われ精神的苦痛を受けた。」という話を人事に訴えてきたのです。
私が双方の話をじっくりお聞きすると、「上司は業務過大をねぎらうために(ポケットマネーで)頑張っている部下をねぎらっていると思っていた(喜んでる部下も多いと思っていた)」「女性社員は、疲れているのに当日断れない雰囲気で誘われるのが辛い」という気持ちのすれ違い部分が見えてきましたので、双方が理解できるように伝えることからはじめました。
そして、
- 業務過大となる時期に残業となるスケジュールを予め提示させ、上司部下ともに日々の業務終了時刻を把握すること
- 慰労会は会社の行事とし、定期開催とする一方で出欠を任意としたこと
とし、以後この部署でのハラスメント問題は聞こえなくなりました。
もし、ハラスメント問題やその火種にお悩みなら、まずはお気軽にご相談ください。
御社の命運を分ける大問題の芽を、今、摘み取ることができるかもしれません。
社会保険労務士
その問題、こじれる前にこうべみなと社労士オフィスに相談してみませんか?
☎ 078-600-2236 8:30〜18:30(土日祝除く)
〒651-0087 神戸市中央区御幸通6-1-15 御幸ビル8階 MAP